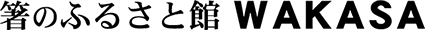若狭塗箸の工程
優美な伝統の技を受け継いだ若狭のお箸
若狭塗箸の特長はなんといっても、貝殻や卵殻を色とりどりの色漆で塗重ねること。十数回も塗重ねられた漆の層を丹念に研ぎ出し磨き上げることで、まさしく美しい海底の様が浮かび上がります。1597年三十郎が考え出したこの技法は前代未聞。当時の人をどれだけ感嘆させたことでしょう。三十郎のしなやかな発想力と技は、21世紀を迎えた今もしっかり受け継がれています。
~木地づくり~
- 原木
- 主に古代若狭塗の場合は孟宗竹、その他にも桜、シタン、タガヤサン等が用いられます。
- 野積
- 切り出した竹を加工前に野外に積んでおくことです。
- 荒切り
- 野積しておいた竹の節を取り除きます。
- 小割り
- 竹を棒状に切断します。
- 仕上げ割り
- 棒状にした竹をさらに刃物で頭を太く、先を細く削ることで、箸の素地が完成します。
~塗り・研ぎ出し~
- 塗り下地
- 漆が竹に吸い込まれないよう、にかわ(動物の油)を素地に塗ります。
- 模様付け
- あわび貝、卵殻、松葉等で模様を付けます。
- 角取り
- 漆の乗りをよくするため、模様付け部分を平らにします。
- 空研ぎ
- 全体を滑らかにするため、さらに研ぎを加えます。
- 合塗り
- 箔下に色彩を出すため、青、赤、黄等の色を塗り重ねます。
- 箔巻き
箔押え
角押え - 金箔等を巻き、はがれないよう、透け漆を塗ります。
- 塗り込み
- 色漆で6~7回塗り重ねます。
- 石研ぎ
- 砥石で研いで模様を出します。この時の力加減が微妙な美しさを創り出すので、1本として同じ物はできません。
- 艶塗り
- 肌のザラつきをなくし艶が出るよう、漆をさらに擦り込みます。
- 炭研ぎ
- 箔のはがれ防止、艶出しに加え、肌を細くするため粉状の炭で研ぎます。
- 磨き
- さらに艶を出すため砥の粉・角粉を手に付けて磨きます。
- 製品
- 完成です。